
投資の本質をついていると思います。
但し、実行に移そうとすると難易度は高い。
まだ、途中ではありますがご参考にして頂ければと思います。
1.二次的思考をめぐらす。
投資の目標は、平均的なリターンを得ることではない。平均を上回るリターンをあげることだ。
その為には、他の投資家とは違った反応や振る舞いをしなければならず、二次的思考が必要。
二次的思考とは?
例1)
・一次的思考:これは良い企業だから株を買おう
・二次的思考:これは良い企業だけど、過大評価されていて割高なので売ろう
例2)
・一次的思考:経済成長率は低下し、インフレ率は上昇の見通しだから売ろう。
・二次的思考:景気見通しは悪いが、他の投資家はパニック売りしているので、今が買い時。
勿論これでは市場をアウトパフォームすることは不可能。
・市場に勝つには、資産価値についてコンセンサスとは違う見方をする必要があり、しかもそれは正確 でなければならない。
・投資プロセスを単純なものだと感じている人は二次的思考の存在自体に気づいていない。常に優れたリターンを達成する為には、二次的思考をすることが必要。
2.市場の効率性(とその限界)を理解する
効率的市場とは?
・市場には数多くの参加者がおり、参加者は情報を同程度入手でき、知的で客観的な目を持ち意欲的で努力を惜しまない。
→情報は直ちに市場価格に反映され、あらゆる資産のリスクとリターンは構成な水準となる。タダ飯がふるまわれることはない。
・著者は、効率的=”動きが迅速で、即座に情報を織り込むという意味”で使うが、”正しい”という意味ではない。
非効率的市場とは?
・市場価格が間違っていることが多く、各資産のリスクとリターンが公正とはならず、タダ飯がふるまわれるときもある。
・筆者は、完全に効率的、あるいは完全に非効率的な市場は存在せず、要は程度の問題だと筆者は考えている。主要な証券市場では、有望株を探すことが時間の無駄と言える程、効率的になりうると強く感じている。
割安資産や掘り出しモノを買う為には、二次的思考を実践し、他の投資家よりも優れた洞察力が必要。
3.バリュー投資を行う
投資の原則
・投資の原則は、『安く買って、高く売れ』 眩いほどに明瞭。
「高い」「安い」という言葉は、何らかの客観的基準が必要だが、それは資産の本質的価値と言える。
→原則は『本質的価値を下回る価格で買い、上回る価格で売れ』に言い換えることができる。
この原則に従うには、本質的価値とは何かを理解する必要がある。
そして、本質的価値を推計することが、投資の出発点として欠かせないプロセスである。
投資へのアプローチ(大きく2つの基本方針に分けられる)
①その株式そのものの値動きの研究に基づくアプローチ
・筆者はその有効性を認めておらず、議論の対象から早々に外しても良い。
1.「テクニカル分析」
ランダムウォーク仮説によると、株価はコイントスの結果と同様にランダムに動く。
10回連続で表が出たとしても、次のトスで表が出る確率は、あくまでも50%
従い、過去の株価変動は、将来の株価変動の予測に全く役に立たない。
2.「モメンタム投資」
強気相場では有効かもしれないが、問題点もたくさんある。
知性に訴える投資アプローチではないことは明らか。そのことを最も良く示す例が、
デイトレーダーだ。 株の動向を追って、むこう数時間で上下どちらにいくのか、一日の中で
何度も賭けをする。そんな方法で儲けようとする人のことが、筆者には全く理解できない。
②その企業の「ファンダメンタルズ」分析に基づくアプローチ
1.バリュー投資
現在の証券の本質的価値を推計し、価格がこれを下回った時に買う投資。
2.グロース投資
将来、価値が急増する証券を見つけ出そうとする投資。
・バリュー投資とグロース投資を明確に線引きすることはできない。
バリュー投資家は、成長性も勘定するし、グロース投資家は、成長性を鑑みて割安感を勘定している。
現在と未来のどちらを重視するのか、程度の問題である。
・グロース投資家は大勝ち狙いが中心、未来を推測することは現状を見つめることよりも難しい。
グロース投資家は、打率は低いが、リターンは高めになってもおかしくない。バリュー投資は、成功した場合でも、リターンは安定的。
バリュー投資は簡単か?
・筆者はバリュー投資を選ぶ。安定的なバリュー投資を成功させるのは簡単か?答えはノーである。
なぜなら、見積もった本質的価値よりも、資産価格が下がった場合「自分の判断は間違っていたかもしれない」と不安が極大化し、下落に耐えられず、結局は投げ売りするはめになる。
・真剣に利益を追求するなら、形のあるものを拠り所にしなければならない。
ファンダメンタルズ分析による本質的価値の推計が最もふさわしい。
感情に流されない着実な投資は本質的価値の推計を正確にできる土台があってこそできるもの。
・本質的価値を正しく推計できること
・本質的価値を決めたら、感情に流されず、それは正しいと自信を持ち”ぶれない”こと
・バリュー投資家が最も高い利益をあげるのは、割安な資産を買い、まめにナンピン買いをしているうちに、価格が分析通りに上昇した場合である。
4.価格と価値の関係性に目を向ける
・資産の本質的価値を正しく推計できるようになったとしても、その資産の価格が本質的価値に対してどの程度の水準にあるのかに注目しなくてはならない。
・どんな資産も高すぎる価格でかえばそれは悪い投資である。そして十分に安い価格で買っても良い投資にならないほど、悪い資産はほとんどない。
・価格には何が織り込まれるのか?
1.テクニカル要因:アマチュア投資家はほとんど知らないが、証券の需給に影響する。
例1)信用取引での追加金に迫られて行う投げ売り。
例2)ミューチュアルファンドへの資金流入。
どちらも、価値とは関係なく証券取引が行われ、価格を変動させる。
最良の投資方法とは、暴落時にどんな価格でもとにかく売らなければならない人から買うことであるが、投げ売り資産を買うことはいつでもできることではなく、投資家としてのキャリアは積めない。
2.心理的要因:本質的価値とは無関係に証券の需給に影響を及ぼす要因。
・心理的要因の重要性はどれだけ協調しても、しすぎることはない。
価格と本質的価値の関係性を理解するうえでのカギは、主として「他の投資家の心を読む」ことにある。短期的には、投資家心理はファンダとは無関係に証券の価格をいかようにも動かす。
・投資の世界で最も重要な学問は、会計学でも経済学でもなく、心理学である。
・将来の価格変動は、この先投資したいと思う人が増えるか減るかで決まる。
投資は一種の人気投票であり、最も危険なのはあらゆる好材料が織り込まれているピーク時に買うことだ。それ以上新しい買い手は現れない。
・最も安全な投資は、誰も欲しがらないものを買えば良い。価格は上にしか行かない。
心理的要因は自分の心にものしかかってくるので、優れた投資家がしなければならないことと正反対の行動を誘発させる。自己防衛する為には市場心理を理解する為に、時間と労力を投じる必要がある。
・ファンダに基づく価値は、証券を買う日の価格を決定する要因の一つにすぎない。心理とテクニカル要因も味方につけられるよう心掛けなければならない。
投資収益が得られる可能性のある方法について考える
・資産の本質的価値の増大で利益を得る
問題は、本質的価値の増大を正確に予測することが難しいこと。
さらに言えば、増大の可能性は一般的には価格に織り込まれている為、コンセンサスとは異なる見方を有していなければ期待はできない。
・レバレッジを利かせる
レバレッジを使うことは、借りた金で資産を買うだけなので投資の質の向上や利益が生じる確率の上昇にには繋がらない。利益や損失を爆発させるだけ。
・保有する資産を本質的価値を上回る価格で売る
そんな価格で買ってくれるカモの到来は、あてにできない。
・資産を本質的価値を下回る価格で買う
これこそが金儲けをするうえで、最も信頼性の高い方法。市場参加者が目を覚まし価格が本質的価値に向かって上昇するのを待つだけ。
但し、経済学者のジョン・メイナードが、
「市場は、あなたが支払い能力を保てる期間よりも長く、不合理な状態を続けることができる」
と言ったように、価格が本質的価値に収斂されるまで、想定以上の時間がかかるかもしれない。
5.リスクを理解する
・投資を一言でいうなら、「未来に対処すること」
→未来を見通せる者などいないから、リスクは避けることができない。
・投資において、リスクに対処することは、一つの絶対に必要な要素である。
リスクへの対処は3STEPある
1.リスクを理解すること←本章
2.リスクが高まったことを認識すること
3.リスクをコントロールすること
・リスクとリターンの関係
・リスクとリターンの関係を示す正しい図は、図表5-1ではなく5-2である。
リスクが高い場合、高い期待リターンが望めるが、リターンが低くなる、場合によっては損失がでる可能性を認識すること。


リスクの定義づけ
・金融理論では、リスクをボラティリティと厳密に定義している。
このリスクの定義について、筆者は異議を唱える。
・ボラティリティが高い投資ほど高いリターンを提供するような価格を市場が形成するのであればその相関性を求める人がいるはずだが、お目にかかったことはない。
・投資家の言う「リスク」とは、資金を失う可能性であると、断言しよう。
リスクとは?
・未来に起こりうるリスクのほとんどは、主観的(人によって変わる)で、みえにくく定量化できない。
・リスク調整後リターンについて、客観的な指標を求めるなら”シャープレシオ”に注目することぐらいしかできない。
・投資パフォーマンスは、様々な要因(地政学、マクロ、企業経営、テクニカル、心理)の組み合わせにより左右される。将来に起きる可能性があることは無限にあるが、現実となるのは1つだけ。
・全ての投資シナリオのうち99%に耐えられるよう正しく設定したポートフォリオが、残り1%のシナリオが現実となったせいで、損失を出した場合、結果的にこの投資は高リスクに見える。
逆に、型破りなシナリオが実現した時だけ成功するようなポートフォリオがあり、これが現実となった場合、向こう見ずな賭けが、保守的で先見性のある行為と誤解されるかもしれない。
・投資した結果が”まぐれ”や”不運”だったのか、”必然”なのか”偶然”なのか誰にもわからない。
天気予報が晴れの確率は70%で、雨が降ったらそれは、当たり?外れ?
晴れであった場合もしかりで、0%か100%でない限り当たりか外れかは、誰にも判断できない。
・有能な投資家は一定の状況下であればリスクを感知し、下記2項目に基づき判断を下すことができる。
・本質的価値の安定性と信頼性
・価格と本質的価値の関係性
リスクを評価できるのは、経験豊富で洗練された二次的思考ができる者だけである。
6.リスクを認識する
・リスクは刹那的で計算できない。従いリスクを認識することは極めて難しい。感情が高ぶっている時なら尚更である。しかし、リスクの認識は必要不可欠である。
・リスクを認識しようとしない投資家には、バフェットの「潮が引いて初めて誰が丸裸で泳いでいたのかがわかる」という言葉を贈りたい。楽観主義者は「潮は二度と満ちない」と肝に銘じるべき。
・リスクの実態は非常に複雑怪奇である。人はリスク認識能力を過信し、リスク回避の為に成すべきことを過小評価する。強気になり、リスクを取りに行けば行くほど、資産価格が上昇し期待リターンは低下する。
・筆者はこれを「リスクのあまのじゃく現象」と呼んでいる。
✔投資家が強気になれば、リスクプレミアム/期待リターンは縮小し、リスクは拡大する
✔投資家が弱気になれば、リスクプレミアム/期待リターンは拡大し、リスクは低下する
・投資リスクが高すぎると皆が言うものが、筆者に最良の投資機会をもたらしてきた。
高リスク/不人気資産の価格は大抵、全く危険ではない水準まで低下し結果最も低リスクな資産になる。
投資リスクは最もリスクが少ないと思われているところで、最大化しておりその逆もしかりだ。
問題は、どんな”価格”で買うかだ。誰もが飛びつくような意見はリターンが低くなる可能性だけでなく、リスクも高くなる可能性を生み出す。
7.リスクをコントロールする
・筆者の考えでは、優れた投資家はリターンを生み出す能力と同じくらいリスクをコントロールする能力を持っている。獲得するリターンに相応する水準よりも低いリスクをとる者こそ、優れた投資家。
高いリスクを取って高いリターンを達成してもほとんど意味はない。
・重要なことは、損失が生じなかった場合でも、リスクが存在していた可能性を認識すること。
相場が悪いときはもちろんだが、相場が良い時期でも急転直下する可能性があるからには、リスクをコントロールする必要がある。
・良い運用の定義を考えた場合、ほとんどの市場観測者は、ベンチマークと同程度のリスクを取って、それよりも高い収益率を達成できることであると考えている。確かにそれは優秀で、アルファを付加価値として加えている。
だが、非効率的な市場では、ベンチマークよりも低いリスクでベンチマークと同水準のリターンを達成することも可能。筆者はこちらこそが優れた運用だと考える。
・リスクの高い資産も十分に安い価格で買えば、良い投資となる。重要なのはそのタイミングがいつかを知ること。よく理解したうえでリスクをとることは、長期で良い投資をするのに最適な試練である。
・リスクコントロールとリスク回避は違う
✔リスクコントロール→損失を回避するのに最適な手段
✔リスク回避→結果として利益回避にもなる可能性がある
投資家の成否は利益をあげた投資のすばらしさよりも、損をだした投資の数と規模で決まる。
巧みなリスクコントロールが、優れた投資家の印である。
8.サイクルに注意を向ける
・人生同様、投資の世界では確実なことはほぼ無い。それでも信じられる原則が2つある。
①ほとんどの物事にはサイクルがあることがやがて判明する
②大きな利益や損失が生じる大きな機会は、周りの者が①を忘れた時
・時として、サイクルの上昇/下降局面が長期化すると、人々は「This time is different」と言い始める。制度、技術、行動の変化により「古いルール」は通用しなくなったと主張する。
やがて、「古いルール」は尚も生きていることが明らかになり、サイクルが動き出す。
要するに、空まで届く木はなく、ゼロになって終わるものもほぼない。結果的には、ほとんどの現象はサイクルに従って起きている。
・サイクルの上昇/下降局面では、ほとんどの場合未来は過去と非常によく似た状況になる。
反転すると判断するのにふさわしいタイミングとして、相場が低迷し周りの誰もがタダ同然の価格で売りたたいている時がそうだ。相場が下降最高の水準にある時に過去に一度も実現していない都合の良い理屈に飛びつこうとするのは危険。人は過ちを繰り返し、それはまた繰り返される。
9.振り子を意識する
・株式市場の地合いの動きは振り子の振動によく似ている。
振り子の軌道の中心は”平均的”な位置だが、その位置に振り子があるのはほんの一瞬。
そして、一端に近づけば遅かれ早かれ中心に向かい動きが反転する。
投資家の心理は振り子の「幸せな中心点」よりも両端に長く位置するように見える。
・筆者は投資における主要リスクを下記2つに集約した。
✔損失を出すリスク
✔機会を逸失するリスク
このうちどちらかをほぼ排除することは可能だが、両方をなくすことはできない。
理想的な世界では投資家はこの2つのバランスを取るが、振り子が起動の一端に達するとどちらかが支配的となる状況が生じる。
・強気相場には三段階のプロセスがある。
1.まず先見の明がある一握りの人が状況が良くなると考え始める。
2.次に多くの投資家が実際に状況が良くなっていることに気づく。
3.最後にすべての人が状況が永遠に良くなり続けると思い込む。
これ以上に的確に言い表すことはできない。
筆者は、「賢明な人が最初にやること、それは愚か者が最後にやることだ」という格言が好き。
振り子が永遠に一方向へ進み続ける、あるいは、一端にとどまり続けると考える者はいずれ大損するだろう。一方、振り子の挙動を理解している者は大儲けする可能性がある。

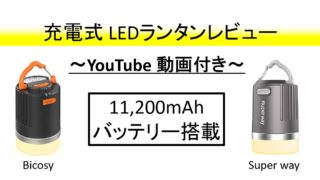
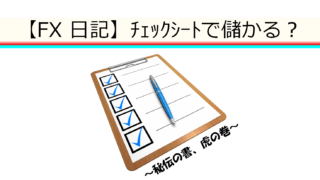
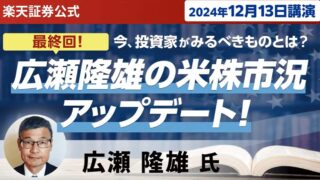







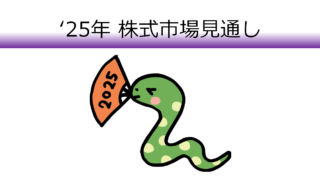



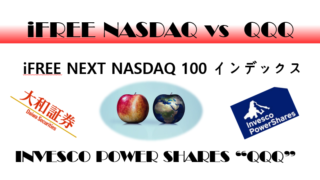
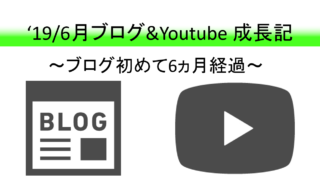


コメント